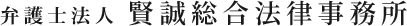被相続人の生前に預貯金の流出があった場合の手続きの選択について
遺産分割・遺留分
1 問題の所在
被相続人の生前に預貯金の流出があった場合に、どのような手続きが取りうるでしょうか。取りうる手段としては、①流出のあった財産は、相続財産の中に残存していると考え、遺産分割協議の中で解決する方法、②相手方に対する贈与があったと考え、特別受益の持ち戻しを求める方法、③不法行為に基づいて損害賠償請求をする方法、④不当利得に基づいて返還請求をする方法が考えられます。
2 手続きの選択
手続きの選択は、理論的には、相手方の主張に応じて、下記の通り振り分けられると考えられます。
第一に、相手方が預金の引き出しへの関与自体を否定した場合には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求といった訴訟による責任追及をすることが考えられます。
第二に、相手方が預金の引き出しへの関与を認めた上で、贈与を受けたという主張をしていない場合には、遺産分割調停において、相手方の預かり金「現金」として、遺産分割の中で解決することが考えられます。
第三に、相手方が預金の引き出しへの関与を認めた上で、贈与を受けたと主張した場合には、遺産分割の中で、特別受益の持ち戻しを求めることが考えられます。
3 相手方が贈与を主張した場合の問題
このうち、問題となるのは、第三のケースです。その中でも、問題となるものとして考えられるのは、下記の2類型です。
第一に、相手方が調停において贈与の事実を否定していたにもかかわらず、訴訟に移行した後、やはり贈与があったと主張した場合です。この場合には、被相続人から相手方に対する贈与の事実が認められれば、原告の不当利得返還請求が棄却されることになりますが、他方で、被告の特別受益がないという前提で既に成立した遺産分割調停等の効力を否定することは容易ではありません。
これについては、被相続人から贈与を受けた事実はないという被告の主張は、そのような主張を前提とした原告の訴訟活動を無にさせるとともに、原告の権利実現を著しく困難にさせるものであるから、訴訟上の信義則に反し、許されないと考える見解があります(名古屋地方裁判所民事プラクティス検討委員会「被相続人の生前に引き出された預貯金等をめぐる訴訟について」判例タイムズ1414号(2015年)74頁以下参照)。
第二に、相手方が被相続人から贈与されたと主張されている場合において、超過特別受益が生じる場合です。受贈者は、贈与の価額が相続分を超過するときは、その相続分を受けることはできないが(民法903条2項)、その反面、相続分を超える特別受益があった場合には、その超過分を返還する必要はありません(谷口知平ほか編『新版注釈民法(27)』(有斐閣・2013年)188頁)。つまり、相手方が、被相続人から贈与を受けたと主張して、相続分を超える価額の預金の引き出しをしていたときは、特別受益の持ち戻しが認められたとしても、引き出された預金の全額について、権利を主張することはできません。
したがって、このような主張がされた場合には、引き出された預金について権利主張をすることは難しいと考えられます。
弁護士: 佐藤史帆