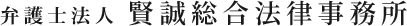相続分譲渡をするにあたり財産開示の内容が要素の錯誤にあたるかについて(判例解説)
遺産分割・遺留分
1 はじめに
本コラムでは、相続分譲渡をするにあたり、財産開示が不正確であった場合の効果について述べた判例を紹介します。
2 広島高裁松江支部平成2年9月25日決定
本件は、「遺産分割協議書」という書面で実質的な相続分の譲渡が行われた事案で、被相続人の預金が約1900万円と説明を受けていたが、実際には約2400万円であったため、要素の錯誤による無効を主張した事案です。
判例では、「遺産分割においては,その分割の対象となる遺産の範囲が重要な意義をもつことに鑑みれば,相続権の行使における意思表示においても,その前提となる遺産の範囲が重要な意義をもち,この点に関する錯誤は,特段の事情がない限り,要素の錯誤にあたるものというべきである。」とされています。
そのうえで、具体的な事情として
①取得金額の決定が一定の合理的な算定基準によるものではなかったこと
②他の相続人らの取得額に関心をもったと窺える形跡がみられないこと
③もともと法定相続分の全額までを要求する意思ではなかったこと
一方において,
④遺産である預金の総額を全く度外視して各自の取得金額を決定したといい切るだけの特段の事情は認められないこと
⑤真実の預金額と抗告人らの誤信した預金額との差額も約500万円と大きいこと
⑥各4分の1ずつのいわば大口の法定相続分を有する相続人であること
を考慮して、本件では要素の錯誤にあたり、錯誤による無効を認めました。
3 東京地裁平成28年2月15日判決
原告が被告に対し、遺産がほとんどないと説明を受けて本件相続分譲渡証書を作成したが、実際には遺産が1億8000万円程度存在していたとして、錯誤無効を主張した事案です。
①原告は、相続人間で遺産分割で揉めていることを聞いていたが、どの程度の遺産があるのかについては関心がなく,面倒なことに巻き込まれるのは嫌だと思っていたこと
②本件相続分譲渡証書の作成に際しても,遺産の内容を確認することもせずに署名押印して返送し,返送時に同封した手紙に早期の解決を願うとの趣旨を記載していたこと
③相続人間で遺産分割で揉めていることを知っていたことからすれば,遺産の具体的な内容には無関心であっても,相応の遺産があることは推測することができ,遺産がほとんどないと誤信することは考えにくいこと
以上の点から、原告が被告に相続分を譲渡したのは,遺産分割をめぐる相続人間の揉め事に関わりたくないとの考えが主たる動機であったことが推認される。そのため、本件では、原告が,Aの遺産がほとんどないと誤信して,被告に相続分を譲渡したものと認めることはできず,仮にこれを前提としても,原告が上記の動機を表示し,これが被告に対する相続分譲渡の意思表示の要素となっていたものと認めることはできない。
4 まとめ
相続分譲渡の際の財産開示が不正確であった場合の効果については、個別の事案によるところが大きいため、お困りの際は弁護士にご相談ください。